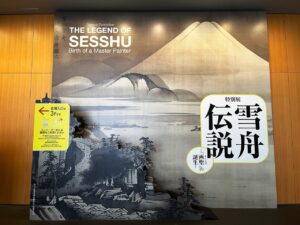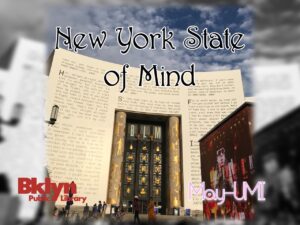ふと、自分が寿命を終えたあとの世界を想像することがあります。
それで、自分のお葬式の日は空が青かったらいいな、と思っています。誰かの記憶の中に「あの人のことはほとんど忘れてしまったけど、お葬式の日の空はすごく綺麗だった」という残り方をしたい、みたいな。
……すみません、本当は「3000年後の人類」について考えようとしていたんです。しかし私にはあまりに大きすぎるスケールで難しかった……。

3000年という歳月について考えようと思ったのは、京都の泉屋博古館の展覧会『泉屋ビエンナーレ2023 Re-sonation ひびきあう聲』を訪れたからです。
同館が誇る住友コレクションの中核をなす中国古代青銅器は、約3000年前に作られたもの。本展では、それらに着想を得た10名の鋳金作家による新作が、着想元となった古代青銅器とともに展示されています。
1つの展示室で古代と現代の作品を鑑賞し、金属という物質的に強い素材と、それよりもずっと脆い人間を対照的に感じ、3000年の時を超えてつながる文化について、どうしても考えたくなってしまいました。
十人十色の作品たち

展示室に入ると、現代の鋳金作家による新作が目に飛び込んできます。大きさや形、さらには色までもが多様な作品たち。出陳作家は以下の10名です。
★出陳作家一覧(敬称略・五十音順)
石川 将士
上田 剛
梶浦 聖子
久野 彩子
佐治 真理子
柴田 早穂
杉原 木三
平戸 香菜
三矢 直矢
本山 ひろ子
一口に「鋳金(ちゅうきん)」と言っても似通った作品は一つとして無く、どの作品も個性のある輝きを放っていることに、ぜひ注目してみてください。

佐治さんの《よりしろ》は、可愛らしい生き物たちが静かに佇んでいるような作品です。古代の青銅器に現れる動物をモチーフにした仮面を身につけています。
仮面は着脱できるということで、内覧会ではその様子を拝見しました。現代の私たちにとって古代の青銅器は鑑賞する古美術品ですが、佐治さんの世界では小さなこの子たちが仮面として「使って」います。古代の青銅器にも命が吹き込まれたように感じられます。

石川さんの《種》には、形や質感に原始的な印象を受けました。ふだんはスッキリとシンプルな形の作品を作ることが多いそうで、展示されていた旧作に比べ、《種》は素朴な造形です。
標本のように整然と並ぶモチーフたちは、具体的に何であると断定できないものの、名前がわからないからこそ惹かれるのだと感じます。言語を体得する前の、赤ん坊として生まれたままの感覚に思いを馳せながら鑑賞しました。
多様な切り口や着想

本展で展示される新作は、出陳作家たちが泉屋博古館を訪れて古代中国青銅器と出会い、着想を得て制作された作品です。
青銅器のどんな側面を取り上げるのか、どんな風に時代を掬い上げるのかなどは、作家によって異なります。各作家の多様な世界観に浸りつつ、約3000年の時を超えた何らかのつながりに、大いに刺激を受けました。

たとえば、 梶浦さんの《地上から私が消えても、青銅》です。いけばなを活けるように形を組み合わせた本作について、梶浦さんは「私が生まれ生きているこちら(2023年)の鋳造技術や社会状況、私の考えなどを、作品を通して古代に伝えようと思いました」とコメントしています。
私たちが約3000年前の青銅器と対峙できるということは、3000年後の人々が現代の作品と対峙するかもしれない、ということでもあります。作品を通じて過去にも未来にもメッセージを伝えるアイデアがとても興味深く、魅力的に感じました。

また、柴田さんは《空白の肖像 古代青銅器と人々》の制作において、古代青銅器が繁栄した時代に存在していたであろう人々に目を向けたそうです。
作り手に注目するところが作家ならではだと感じますし、彼らの日常はたしかにあったはずなのに、今はわからなくなっていることにハッとしました。本作のいつまでも眺めていたくなる柔らかな形は、名も無き作り手の暮らしに私たちの想像をいざなってくれるように思います。
次の3000年を想像してみる

……と思ったけれど想像できなかったことは、冒頭でお話ししたとおりです。しかし金属という丈夫な素材なら、3000年の時を経ても姿形をそのままに生き延びられるのかもしれません。
そのとき当然私はいないし、人類も生き残っているのか、私にはわからないです。もし生き残っていたり、そうでなくても別の知的生命体が地上で繁栄していたとしたら、本展で展示された現代作家の作品は、彼らの目にどのように映るのでしょうか。

たとえば、杉原さんの《猫鎛》です。家族のひとりである愛猫のにゃんまる君を主なモチーフにした本作には、愛を象徴するようにハートが散りばめられています。
ご家族に作品のモチーフとなる動物のヒントを尋ねたところ、奥さまからは「鳥」、お嬢さまからは「うさぎとユニコーンとマーメイド」との回答を得たそうです。両方とも本作に刻まれていますが、「うさぎとユニコーンとマーメイド」はキメラのように合体しています。
作品を見た3000年後の研究者たちが、「この幻獣はいったい何の神話を出典としているのだろう……」と真剣に悩む場面を想像したくなりませんか。私は帰りに迂回して蹴上インクラインをとろとろ歩きながら、うっとりと空想に浸っておりました。
答えは「家族愛」などだと思いますが、3000年後の研究者は辿り着けるのでしょうか。私などは、辿り着けないほうにロマンティックを感じてしまいます。
まとめ

泉屋博古館では、中国古代青銅器を単なる古美術品としてでなく、現代へ受け継がれた金属工芸の原点として捉えているそうです。
時代にとらわれない芸術性の紹介と教育普及に努める活動の一貫として、2021年に『泉屋ビエンナーレ2021 Re-sonation ひびきあう聲』を開催。今回の展覧会は第2弾となります。本記事で紹介できなかった作品も個性があって魅力的ですし、ぜひ会場で実物をご覧いただければと思います。
古代青銅器と現代の作品をあわせて鑑賞できるのみならず、現代の作家の目を借りて古代の作品を鑑賞できる機会となっています。銀閣寺や南禅寺へも好アクセスな同館で、「時」に思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。
【展覧会情報】
泉屋ビエンナーレ2023 Re-sonation ひびきあう聲
会場:泉屋博古館(京都・鹿ヶ谷)
会期:2023年9月9日(土)〜10月15日(日)
休館日:月曜日(9月18日、10月9日は開館)
9月19日、10月10日
開館時間:午前10時 ~ 午後5時(入館は午後4時30分まで)
展覧会ウェブサイト:https://sen-oku.or.jp/program/2023_biennale/
トップビジュアル:梶浦聖子《地上から私が消えても、青銅》(部分)
![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)