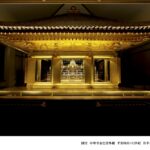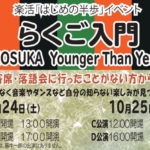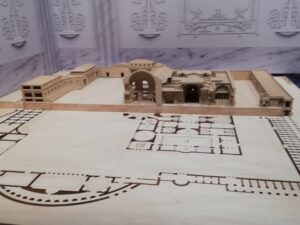19歳でクリスチャン・ディオールに才能を見出され、その後継者としてわずか21歳で、ブランドのチーフ・デザイナーに就任。その数年後には、自身のメゾンを立ち上げ、2002年に引退するまでの約40年間、「モードの帝王」であり続けたイヴ・サンローラン。
そんな彼は、まさに「天才」という言葉がふさわしい。
現在、六本木・国立新美術館では、彼の没後初となる展覧会が開催されている。
なぜ、イヴ・サンローランは、「天才」なのか。彼を「帝王」として、常にモードの最先端に立つ存在たらしめたものは一体何なのか。
今回は、展覧会の内容を紹介すると共に、それらに対する答えを探していきたい。
①師ディオールの後継、そして独立へ
イヴ・サンローランは、1936年、アルジェリアの港町オランで生まれた。内気で感受性が強い彼は、絵を描くことが好きで、13歳の時には自ら挿し絵や装丁を手掛けた絵本を制作している。
やがて、その興味の対象はファッションへと向かうようになり、17歳の時には、パリの国際羊毛事務局のコンクールに挑戦。ドレス部門で3位を獲得している。
その翌年、パリに移住した彼は、エコール・ドゥ・ラ・シャンブル・サンディカル・ドゥ・ラ・クチュールに入学。さらには国際羊毛事務局のコンクールに再挑戦し、ドレス部門で1位と3位を得た。
この事がきっかけになって、サンローランは、審査員の一人を介して、クリスチャン・ディオールと出会ったのである。
ディオールは、まだ20歳にも満たない彼の才能を見抜き、早速自分のもとに就職させた。サンローランも、戦後のパリのオートクチュール界のトップに立つディオールを尊敬し、彼から多くのことを学んだ。
1957年、ディオールが亡くなると、21歳のサンローランは、彼の実質的な後継者として、メゾンの新たなチーフ・デザイナーに就任し、翌年1月の春夏コレクションを取り仕切ることとなる。
尊敬する師を失っただけではなく、その後継に指名されたことで、彼に大きなプレッシャーがのしかかったであろうことは、想像に難くない。
しかし、彼は重圧に潰されることはなかった。
チーフ・デザイナーとしての初仕事の中で、彼は「トラペーズ・ライン」を発表するのである。
「トラペーズ・ライン」とは、肩から裾に向かって緩やかに広がる台形のシルエットを指す。
その代表格が、「品行方正」シャツ・ドレスである。

© Yves Saint Laurent © Alexandre Guirkinger
女性の身体を隠す、緩やかで流れ落ちるようなラインは、これまでにはないものだったが、そのシンプルで明快なフォルムや上品さは女性たちの心を強く捉え、新聞でも絶賛された。
彼は「トラペーズ・ライン」を通して、11年間の活動期間の中で、「Aライン」、「Hライン」など、「ライン」というテーマに沿って作品を発表し続けた師ディオールのやり方を引き継ぎながらも、「新たなスタイル」を打ち出してみせたのである。
この後も、ディオールで6つのコレクションを手掛けた彼は、1961年には、ついにディオールの枠を飛び出し、自分自身のメゾンを立ち上げる。
そして、1962年には自分の名を冠した初のコレクションを発表する。
発表した中には、船乗り(水兵)の仕事着をベースに、着やすく洗練された女性の服へと進化させた、サンローランのスタイルの象徴とも言うべき紺色のピーコートや、「シャネル以来最高のスーツの作り手」と絶賛されたデイタイム・アンサンブルが含まれていた。

© Yves Saint Laurent © Alexandre Guirkinger

「帝王」サンローランの歩みは、まさにここから始まったのである。
②サンローランの「旅」ーーーインプットとアウトプット
サンローランは、そのキャリアを通じて、アフリカやロシア、スペイン、アジアなど、しばしば異国趣味を取り込んだデザインを発表しており、それらは第四章「想像上の旅」で見ることができる。
しかし、彼自身は旅行はあまり好んでおらず、モロッコを除いて、はるばる現地に足を運んだわけではなかった。
彼にとっての「旅」とは、書斎での読書や美術作品の収集を通じた「想像上」のものだったのである。
挿絵や文章、美術品を介して、彼は想像を膨らませ、はるか彼方の美しい世界の中で自由に遊ぶことができた。そして、その「幻想」を彼は魅力的なデザインへと昇華させて行ったのである。
「アフリカ」をテーマとする1967年の春夏コレクションは、その一例である。

彼はここで、西洋の伝統的なカッティング技術をベースに、木のビーズやセルロイドなどの素材を用いた刺繍をほどこすことで、従来のオートクチュールにはない新しさを付与している。
彼の「旅」は、異国だけではなく、時には過去の歴史にも及んだ。
古代ギリシア・ローマの彫刻に見られるアンティーク・チュニックや、19世紀に流行したスカートの後ろを大きく膨らませるバッスルスタイルなど、過去のファッションにもヒントを求め、20世紀に生きる女性たちのための服として、新たな命を吹き込んだのである。


どんな「天才」であっても、何もないところから新しく何かを生み出すのは、不可能である。
今回の展覧会に出品されている110点のルックの根にあたる部分には、幅広く膨大な量のインプットが存在する。
それらの「源流」を意識し、どのような形でアウトプットされたか。
それを考えていくのも、展覧会の一つの見方である。
③アート(芸術)との関わり
サンローランについて語る上で、欠かせないワードの一つとして「アート(芸術)」が挙げられる。
芸術作品に触れることで、人の感性は大いに刺激される。それによって得られる「感動」は、クリエイターたちにとって、新たな創作のエネルギー源となる。
サンローランも、美術や演劇、文学など、あらゆるジャンルの芸術に関心を抱き、インスピレーションの源としていた。
特に美術に対しては並々ならぬ関心を寄せ、そのキャリアの中で、美術作品を「引用」した、芸術家たちへのオマージュとも言うべきデザインをしばしば発表している。
その代表格として、1965年に発表された「カクテル・ドレス-ーーピート・モンドリアン」を見てみよう。
モンドリアンは、20世紀のオランダの画家で、『赤・青・黄のコンポジション』のように、黒い垂直線と水平線によって分割された画面に赤・青・黄色の三原色のみ、と極限まで切り詰めた要素のみで構成された作品群で名高い。

*展覧会には出品されていません

このカクテル・ドレスも、単に作品の構成をなぞるだけではなく、無駄な装飾を削ぎ落とし、直線的でシンプルなシルエットを採用することで、二次元の画面が持つストイックさを、衣服という三次元のジャンルへと移し替えている。
絵を描くことが好きだったという少年時代を考えても、サンローランは、美術家たちに憧れや共感を抱いていたであろうことは想像に難くない。
だからこそ、彼はデザインを通して、モンドリアンやピカソ、ゴッホ、ボナールら名だたる巨匠たちに近づき、対話し、彼らから学ぼうとした。
更に出来上がった服とアクセサリー類の組み合わせを考え、実際に女性にまとわせることで、彼は新たな「作品」を作り出した。
眼を楽しませる美しさと、衣服としての実用性を兼ね備えたそれは、「芸術」と言っても過言ではないだろう。


クリスチャン・ディオール、世界の国々、積み重ねられてきたファッションの歴史、そして芸術家たち。
サンローランは、あらゆる存在を師とし、彼らから積極的に学び、吸収した上で、それらを「女性が『着たい』と思う服」へと昇華させ続けた。
常に幅広く学び続け、自分の感性を磨き続けること(インプット)、そして、「現代を生きる女性」というターゲットや、彼女らの求めるものを意識し、それを「軸」として定めていたこと。
これらを継続できたことが、彼が「天才」と呼ばれる由縁であり、数十年に渡って、彼を「帝王」たらしめた土台と言えよう。
ここに紹介できたのは、彼が作り出したもののごく一部に過ぎない。
続きは是非ご自身の目でご覧いただきたい。
©︎ Musée Yves Saint Laurent Paris
展覧会情報
イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル
会期:2023年9月20日(水)~12月11日(月)
開館時間:10:00~18:00
※毎週金・土曜日は20:00まで ※入場は閉館の30分前まで
会場:国立新美術館 企画展示室1E 〒106-8558 東京都港区六本木7-22-2
休館:毎週火曜日休館
HP:https://ysl2023.jp/
メインビジュアルクレジット:ジャケット 1977年に行われたジジ・ジャンメールのショー『ローラン・プティのショーに登場するジジ』のためのデザイン© Yves Saint Laurent © Sophie Carre
![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)