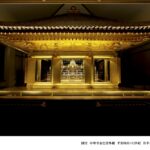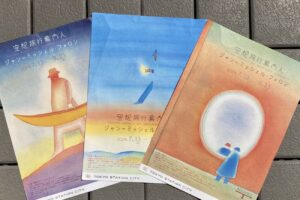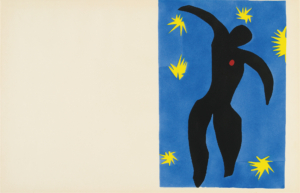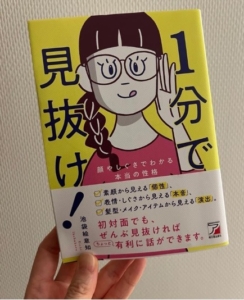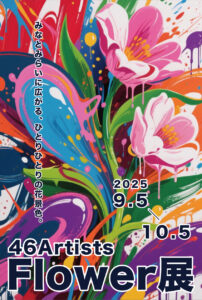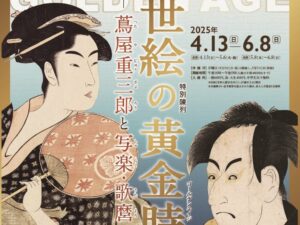明治時代、日本では急激な西洋化が進み、その影響は美術界にも及んでいた。
西洋の油彩画が流行する一方で、従来の日本伝統の美術は「時代遅れ」、「ローカル美術」と見なされがちだった。
そのような中で、西洋画に対する「日本画」というものを意識する動きが出てくる。
そして、旧習に縛られた画壇の革新に、大きな役割を果たした人物が、竹内栖鳳だった。彼は新たな「日本画」の表現を追求し、その卓越した筆力でもって、数多くの作品を生み出すと共に、上村松園をはじめ多くの弟子たちを育て上げ、近代京都画壇の礎を作りあげたのである。
今回は、京都市京セラ美術館で開催中の『京都市美術館開館90周年記念展 竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー創世』展から、出品作を数点選び、彼が成し遂げた「革新」の詳細に迫ってみたい。
①「写生」という軸
竹内栖鳳は、1864年に京の料理屋の子として生まれた。
幼い頃から絵を描くのが好きで、17歳の時には四条派の幸野楳嶺の画塾に通い始める。
日本の絵師たちは、多くの場合、画派の伝統や師の教えを重んじ、そこから逸脱することを避ける傾向が強い。
しかし、栖鳳は違った。彼は四条派だけではなく、円山応挙らの江戸絵画、雪舟の水墨画などの古典作品にも関心を向け、積極的に模写を行ったのである。
こうして、あらゆる画派の技を彼は学習し、それぞれの長所を寄り合わせることで、彼は自らの新しい画風を作り上げていった。
その際に、軸となったのが「写生」だった。
「写生」とは、植物や動物など、事物(モチーフ)を観察し、見たままに写し取ることである。江戸時代、円山応挙がこの「写生」を重んじた新しい画風によって、当時の京で人気を博し、四条派の祖・呉春も、応挙の影響を受け、「写生」を取り入れた。
以後、「写生」は弟子たちによって受け継がれ、栖鳳もまたその系譜に連なる一人として、「写生」に力を入れ、生涯に残した写生帖は100冊以上になる。
モチーフの観察と、それを紙に写し取ることのおびただしい積み重ねは、彼の絵の技術だけではなく、瞬間的な動きを捉える観察眼をも鍛えた。その成果は、2羽の軍鶏が宙に飛び上がり、戦う様を描いた〈蹴合〉に見ることができよう。

また、展覧会出品作の中で、もう一点注目したいのが、〈虎・獅子図〉である。虎も獅子(ライオン)も、江戸時代以前にも描かれてきたモチーフである。


しかし、どちらも日本にはいない動物であり、絵師たちは、実際に生きている姿を見て描いたわけではない。
では、どうしたのか?
虎の場合は、毛並みは舶来の虎の毛皮をもとに、生態は猫を参考に描かれたと考えられている。

一方、獅子(ライオン)は、古くは神獣「唐獅子」として、インドライオンをモチーフに、装飾化・図案化した姿で描かれてきた。有名な作例としては、狩野永徳の〈唐獅子図屏風〉が挙げられる。

しかし、どちらも実際の生態からは程遠い。栖鳳自身も、特に「唐獅子」の長い歴史の中でパターン化された描き方に不満を抱いていた。
時代は変わった。
古い「型」や「常識」を捨て、一から新たに向き合い、観察し、描いていくべきではないか。
そのような考えに至ったのは、1901年にヨーロッパを旅したことがきっかけだった。
この時に、彼は動物園で生きているライオンを見て、写生する機会があり、帰国後、その経験をもとに、この〈虎・獅子図〉をはじめ多くの獅子図を描いていく。
唐獅子のたてがみが巻き毛として描かれていたのに対し、栖鳳が描く獅子のそれは、一本一本が細く波打つような線で描きこまれ、手を伸ばせば実際に触れられそうな錯覚をも起こさせる。
開いた口からは生暖かい呼気が感じられそうであり、「体臭まで描ける」という栖鳳自身の言葉を実証しているとも言えよう。
〈唐獅子図屏風〉などを見慣れた日本人たちに、これら一連の獅子図は、どれほど大きな衝撃をもたらしただろう。彼は、古い伝統に学びつつもその「型」を破壊し、新たな表現をここに切り開いてみせたのである。
②ヨーロッパへ
「日本画」を西洋絵画と対抗できるだけの地位に引き上げるためには、日本国内で古典的な絵画に学ぶだけでは不十分だった。
西洋絵画にあって、日本画にないものとは何か?日本画の弱点とは何なのか?
それらの問題に対する答えを得るには、一度日本の外に出ることが必要だった。
1901年、彼はヨーロッパに渡り、数か月かけてフランスやドイツ、イタリアなど各国をめぐった。
旅というものは、見聞を広める機会になるものだが、特に栖鳳にとっては、レオナルドやラファエロ、ターナーら西洋絵画の名だたる巨匠たちの作品に直に触れるまたとない機会となった。
また、訪れた先で美術作品を見るだけではなく、彼は「写生」を欠かさず行っていた。そして、帰国後には、それらの「写生」をもとに、西洋の風物や風景を日本画の画材で描いた作品を制作し、注目を集めたのである。


この<羅馬之図>は、その一つである。
夕暮れ時の穏やかな時間、野原にはアーチが連なる崩れかけた建物が聳えている。前景に配された背の高い木々がはっきりと描かれているのに対し、遺跡は画面の奥、霧の中からぼんやりと浮かび上がるかのように描かれている。
セピア色の色調に加え、右隻の空を群れ飛ぶ鴉や、左隻の前景には山羊と共に草をかき分けながら家路へと向かう女性の姿などの細部は、扱いは小さいながらも、作品全体の物悲しい雰囲気をより強めている。
国であれ人であれ、どんなに栄えたものでも、最後は滅びの時を迎える―――漢詩や日本の『平家物語』でも描かれてきた「栄枯盛衰」のテーマが、この異国の地を描いた作品からは浮かび上がってくる。
③人物画への挑戦
動物画で特に名高い栖鳳だが、人物画にも挑戦している。
人間を描くにあたっても、その根には、動物画と同様に、生きている人間の身体と直に向き合い、観察し、ありのままを写し取る「写生」があった。
1901年のヨーロッパ旅行中、ドレスデンの美術学校で、裸体デッサンの授業の見学した彼は、服を着た人物を描く際に、その下にある裸体の筋肉の動きを意識する必要があることを実感し、これからの日本画においても生身のモデルを使うことを提唱した。
その最初の実践例が、<アレ夕立に>である。

これは、舞妓をモデルに描いた作品で、腰を落とし、広げた扇を掲げて顔を隠す一瞬の動きが捉えられている。青地に白い芙蓉の花を配した着物や、金と赤で彩られた着物など、鮮やかな色彩が目を引く。が、よく注意して見ると、ゆったりした着物に隠されている、量感のある肉づき、膝や肘といった関節の曲がる様を思い描く事ができ、身体を立体的・現実的な存在として捉えていることがわかる。

一方、こちらの<絵になる最初>では、絵のために呼んだ女性モデルが着物を脱ぎ、裸体になる時の一瞬の恥じらいを捉えている。
脱いだ着物で身体の前を隠し、翳した左手の下から、上目遣い気味に相手をそっと見やる。この微妙な表情は、男性である栖鳳だからこそ目にし、描けたもの、と言えるだろう。
得意なジャンルとして、強い思い入れと自信を抱いていた動物画。
旅先で触れた各地の風景を題材にした風景画。
そして、どちらかと言うと、「苦手」と認識していた人物画。
どのジャンルにおいても、栖鳳は過去の巨匠たちの画風に学びながらも、それに縛られず、常に実物と直に向き合うことを基本として、自ら果敢な挑戦を続けた。
そのようにして生まれた作品は、いずれも強いエネルギーに満ち、「日本画」の可能性というものを提示してくれている。
まさに、彼は近代日本画における「変革」の体現者と言えよう。
展覧会詳細
京都市美術館開館90周年記念展「竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー」
会期:2023年10月7日(土)~2023年12月3日(日)
(前期:10月7日~11月5日、後期:11月7日~12月3日)
会場:京都市京セラ美術館 本館 南回廊1階
開館時間:午前10時~午後6時(最終入館は閉場の30分前まで)
休館日:月曜日(祝日の場合は開館)
ホームページ:https://kyotocity-kyocera.museum/exhibition/20231007-20231203
![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)