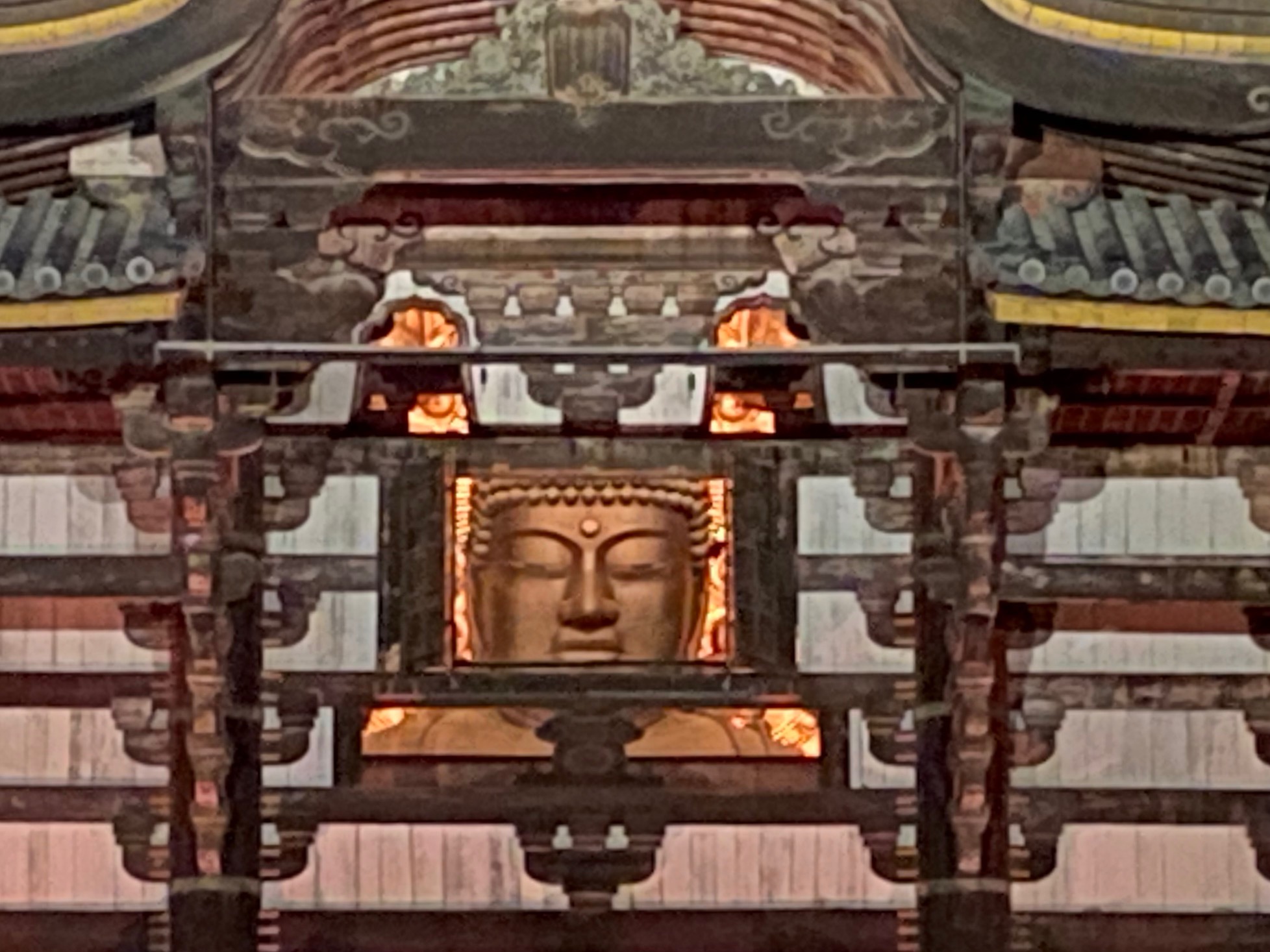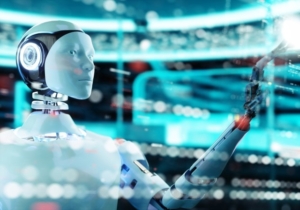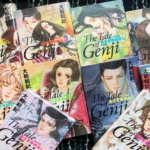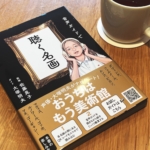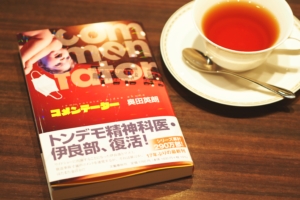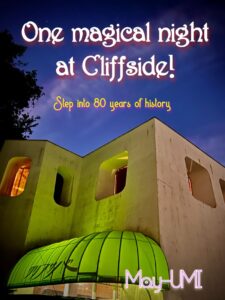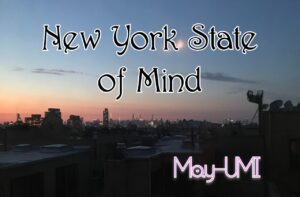ダ・ヴィンチも観相学を研究していた
レオナルド・ダ・ヴィンチが、顔と性格を関連づける「観相学」を研究していたことは有名です。ルネサンス時代には「観相学」が流行しました。16世紀にイタリアのナポリで、博学者で医師のデラ・ポルタという人が「人の顔は、どういう動物に似ているかによって、性格がわかる」と言いました。

17世紀にはフランスの画家、シャルル・ル・ブランが、「ライオンに似ている人は、ライオンのような性格をしている」「フクロウに似ている人は、フクロウのような性格をしている」と。

そもそもライオンの性格とフクロウの性格がよくわかりませんよね(笑)
科学的にまったく理解不能です。それでも当時の科学者たちは「顔と内面」の関係性について真剣に研究していたのです。
顔は機能的に作られる
さて、今回は、顔は機能的に作られるというお話です。
草食動物と肉食動物では顔の特徴が違います。草食動物のシマウマは顔が縦長です。人間でも超面長の人を馬面というように馬の顔は縦に長い。馬の顔が縦長なのは、立った状態のまま水を飲んだり、草を噛みやすいように細長いデザインの輪郭になっています。
いっぽう、肉食動物のライオンは、獲物に噛みついて殺し、肉を食いちぎって食べるために、顎が頑丈で口まわりの筋肉が発達している必要があります。だからライオンの顔は横幅があり、顎がガッシリとした顔のデザインになっています。

次に目の位置について解説します。シマウマの顔は、自分を狙ってくる敵(ライオンやヒョウ)をすぐに発見して逃げられるように、視界が広くなる目が左右についたデザインをしています。

逆にライオンの顔は、獲物を捕らえて攻撃しやすいように、目が前方についたデザインをしていて、そのぶん視界が狭くなっています。
デザインと印象
このように自然界で暮らす動物の顔は、機能的にデザインされているのです。では、あなたはそれぞれの“機能的にデザインされた顔”についてどんな印象を持っているでしょうか。目と目の間が寄ったライオンの顔は、強くて賢い印象を与えます。目と目の間が離れたシマウマの顔は、穏やかな印象を与えます。
人間の顔も同じで、目と目が中央に寄った顔は知的でカッコイイ印象になり、目と目の間が離れた顔は優しくてかわいい印象になるのです。

顔と性格は相互に関係しあっていることから、私たちが感覚から得られる印象とその人の本質はニアイコール……まではいかないけど、それなりに似たような傾向があると私は考えています。
霊長類の顔
顔は機能的に作られる。肉食動物は目が前に、草食動物は目が横に。ならば、なぜ、猿の目は前方についているのか?

サルやヒトの霊長類の目が前方にあるのは手を使うからです。サルは手で餌を確保し、手で餌を口に運びます。ちなみにほとんどのサル類は、葉っぱ、果物、種子、昆虫、小さな脊椎動物を食べる雑食です。
霊長類は視覚の動物
サルから進化したと言われている人間も、手を使って物を作ったり、箸やスプーンを手で持って食事をし、手でペンを持って字を書いたり、本を持って読んだり、パソコンしたり、スマホを見たりしています。体の構造上、目が前についていたほうが便利です。
霊長類は他の哺乳類と比較すると、嗅覚情報、聴覚情報よりも視覚情報が重要な視覚の動物と言えます。目でいろいろ見て目から情報を得て判断し、行動しているのです。
進化論について
「機能的に」という話でいうと、シマウマはライオンなど外敵がやってきてもすぐに逃げられるように、立ったまま地面の草を食べるため、顔が長くなったと言われています。
「キリンの祖先は、高い所の葉っぱを食べるために首が長く進化してキリンになった」と進化論では言われています。

この説に真っ向から反対しているのが、“科学界のインディ・ジョーンズ”と呼ばれる生物学者の長沼毅先生(広島大学大学教授)です。
「だったら樹によじ登るキリンが出てきたのか?」
「首の長いキリンは水を飲むのが大変ではないか」と。
長所と短所は表裏一体
確かに首が短く顔が長いシマウマと違って、首が長いキリンは水を飲むのが大変です。キリンは首を短くして顔を長くし、シマウマのような体型になれば、水が飲みやすくなります。でも、それだと今度は高い所の葉っぱを食べられない…。
長沼毅先生の説は
「遺伝子の突然変異。キリンが望んだ突然変異ではない。ある個体に突然変異があり他の個体とは違って首が長かった。意図せず生まれてきたデメリットをメリットに変えて新たなライフスタイルを開拓していったのが生き残っている」
「もって生まれたカタチでなんとか生き延びる」
「長い首で生き残るしかないという勇気ある1個体の末裔がキリン」
私はどちらかというと、長沼先生の説を支持します。
人間も親からもらった顔を不満に思うのではなく「もって生まれた顔でなんとか生きていく」「自分の顔を愛して生きていく」。これが人間の生き方だと思います。
「池袋 絵意知の顔面学講座」は月1回の連載シリーズ。第1回、第2回連載はこちらです。合わせてお楽しみください。
![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)